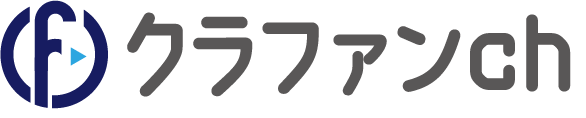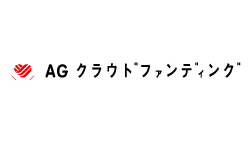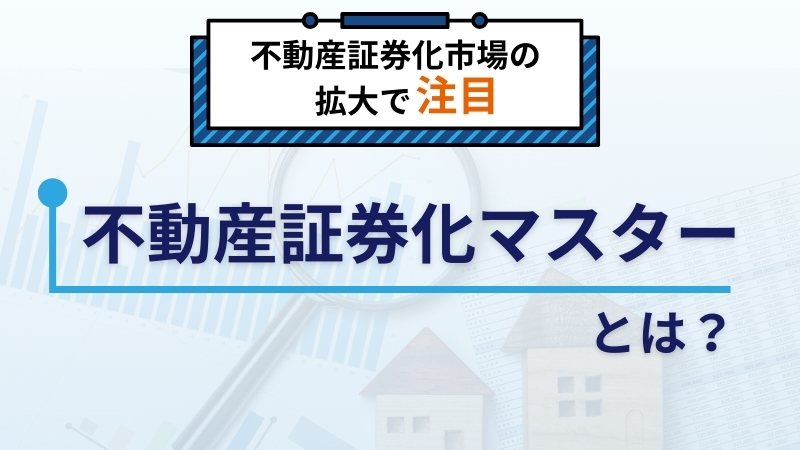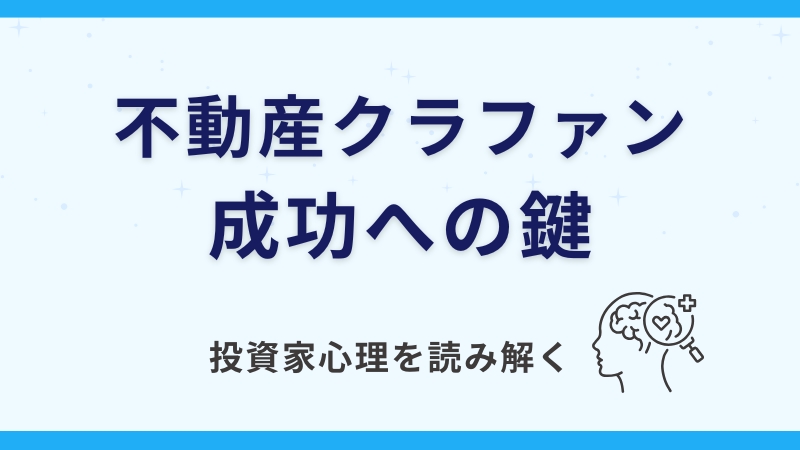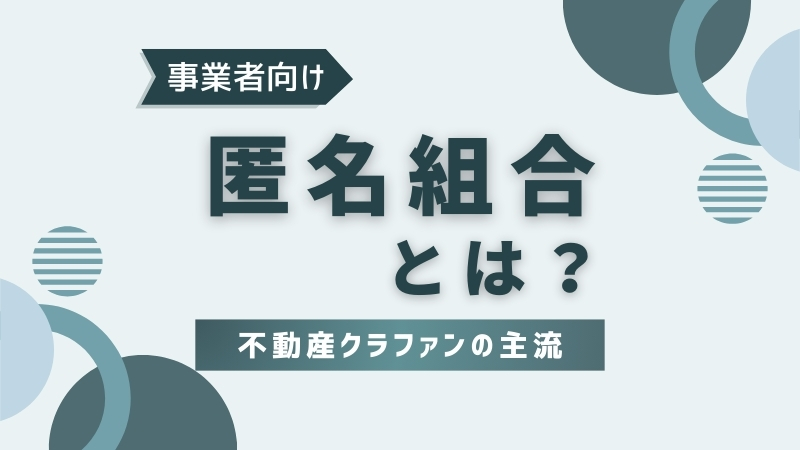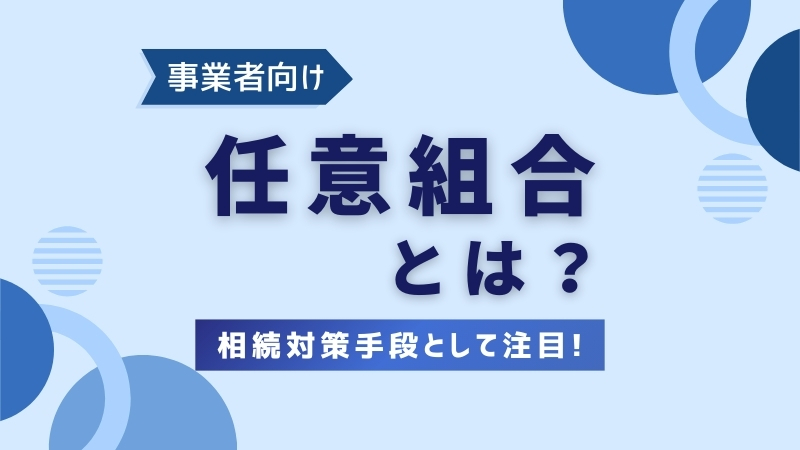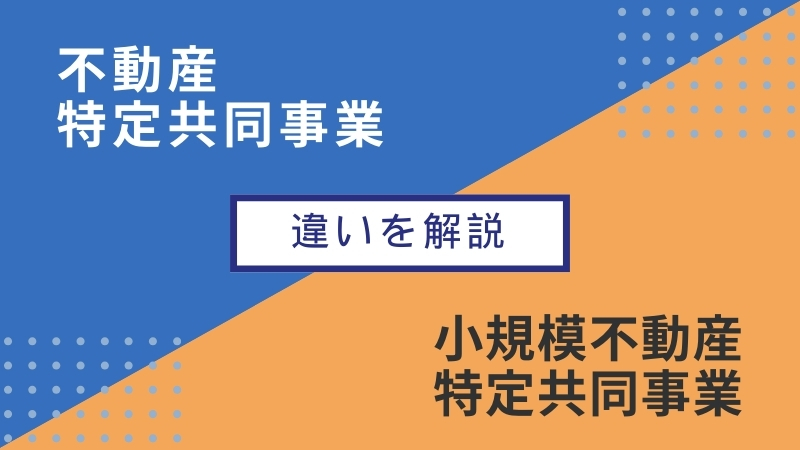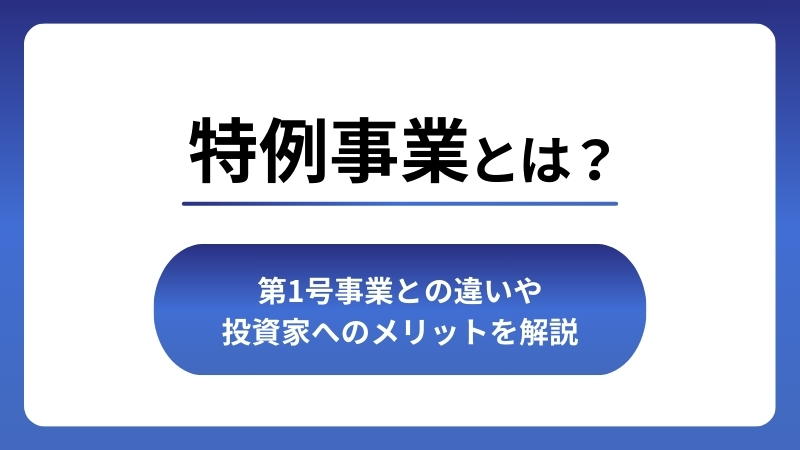しかし事業としての立ち上げを検討していると、
クラウドファンディング自体はまだまだ若い産業で、比較的レガシーな産業である不動産投資との融和の動きは始まったばかりですが、なぜクラウドファンディングは不動産事業者の関心を集めているのでしょうか。
この記事では、40社以上のクラウドファンディング事業化支援を行う中で聞こえてきた実際の声をもとに、その理由をまとめました。
不動産クラウドファンディングに事業者の参入が相次ぐ3つの理由
①新規顧客の獲得・育成がしたい!

不動産事業者にとってクラウドファンディングには、新規顧客となる投資家層を集め、小口投資を通じた成功体験を提供することで、多額の資金を必要とする不動産投資商品の顧客へと育成するマーケティングの意図があります。
不動産クラウドファンディングによって、幅広い層の投資家を獲得可能です。
不動産クラウドファンディングに取り組む投資家には、リスクをできるだけ回避し、わずかな額であっても不労所得を得たいという小口投資のニーズがあります。
通常の不動産投資であれば、投資家は富裕層が多く、物件に投資する際には多額の資金を金融機関で借り入れて物件を購入するケースがほとんどです。
しかし、不動産クラウドファンディングの場合、一口1万円からという少額の投資を不特定多数の投資家から募り、不動産事業者が物件を取得・運用していくというモデルであるため、通常の不動産投資に比べて障壁が圧倒的に低く取り組みやすいことが特徴として挙げられます。
また、不動産クラウドファンディングは対面での書類手続きが一切存在しないため、面倒なプロセスなしで簡単に投資を始められることから、若年層の投資家から人気を博しています。
彼らは日常的にスマートフォンなどを通じてITサービスに慣れ親しんでいるため、低リスクかつオンラインで展開される不動産クラウドファンディングとの相性は抜群です。
不動産クラウドファンディングとはいわば不動産投資の体験版のようなもので、不動産クラウドファンディングで成功体験を積んだユーザーを、よりリスクの大きい不動産投資へと誘導することができます。
投資初心者にとって入口とも呼べるクラウドファンディングを通じて新規顧客を集められれば、長期的な視点で見た場合、不動産投資の顧客が増え、不動産事業者側のリターンも大きくなります。
こうしたマーケティングの手段としての不動産クラウドファンディングの活用が今後も期待されます。
②地方物件・老朽化物件も取得し、運用したい!

不動産クラウドファンディングの仕組みは簡単に言えば、不動産特定共同事業法の要件を満たし免許を得て、システムを構築しサイトを作り投資家を集め、自社で取得・付加価値を与えた物件に投資をしてもらい、賃料収入や売却益を分配するというものです。
一見簡単そうに見えるプロセスですが、事業構築の最初のフェーズである不動産特定共同事業法の免許を得る際に数か月の期間がかかってしまい、国土交通省から許認可が下りず離脱してしまう事業者も多いです。
決して楽な道のりではありません。
免許取得のためにも、法律に準拠しセキュリティ対策の万全なシステムの導入や弁護士のサポートは不可欠となってきます。
投資家からの熱視線もあるので、しっかりとマーケティングに取り組めば、事業が成功する確率は非常に高くなります。
③ITを用いた新規事業を創りたい!

クラウドファンディングは、金融とテクノロジーの融合を意味するFintechというジャンルに分類されます。
Fintechは近年、サービスをより展開しやすいよう法制度が段階的に整備されてきてはいますが、まだまだ若い分野です。
しかし、どのような業界でも、技術革新が進んでいる現代においては、ITと持ち前の事業ノウハウを掛け合わせた新しいサービスを作り、時代の変化に柔軟に応えていかなければなりません。
そこで不動産事業者から注目されているのが、対面での手続きが必須であった不動産投資を完全にオンライン化したクラウドファンディングなのです。
ITと聞くといささか難解な印象を受け、セキュリティー面の心配も感じるかもしれませんが、サービスの仕組みを弊社のようなシステム事業者や、法律のプロフェッショナルである弁護士と共にしっかりと整えていくことで、投資家に利便性や安全性など大きなメリットを内包したサービスを提供することが可能となります。
たとえ現時点で自社にITのノウハウがなかったとしても、法律に基づいて電子取引業務に適した組織体制を構築すればクラウドファンディング事業を運営可能です。
他社の事例にも目を通しながら、事業の見通しを立てていきましょう。
まとめ
この記事では、不動産クラウドファンディングに事業者の参入が相次いでいる理由について解説してきました。
クラウドファンディング事業は、従来提供しづらかった物件をインターネット上で販売することができるうえ、投資家のリストを取得することも可能となるなど、将来的なメリットが大きいです。
法律やシステム開発・導入のプロフェッショナルと連携し、魅力的なサービスを作っていきましょう。
グローシップ・パートーナーズでは、不特法の免許取得支援やシステム導入だけではなく、マーケティング支援もさせていただいておりますので、クラウドファンディング事業立ち上げの際は是非お気軽にご相談ください。
導入検討に当たって参考になる記事はこちら↓
不動産クラウドファンディングで投資家から出資を募る形式は、匿名組合と任意組合の2種類が存在します。それぞれ性質が異なり、メリット・デメリットが存在します。この記事では不動産クラウドファンディングでファンドを募集する際の2つの[…]