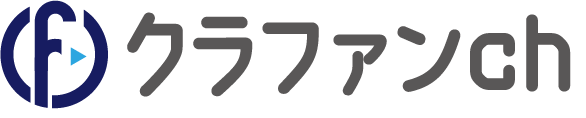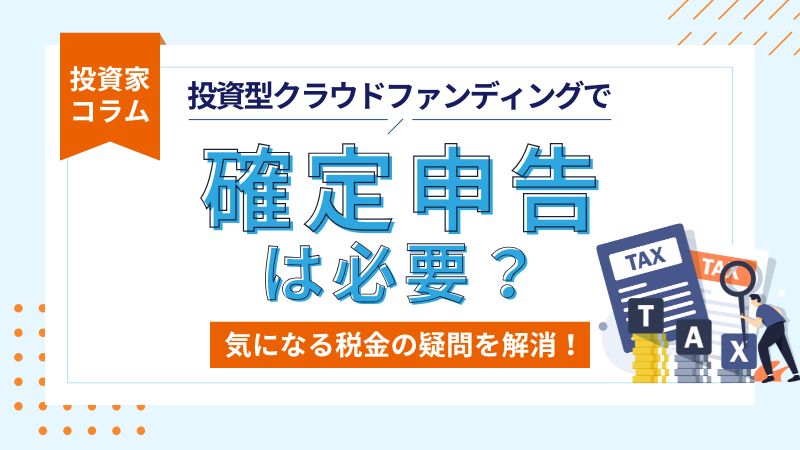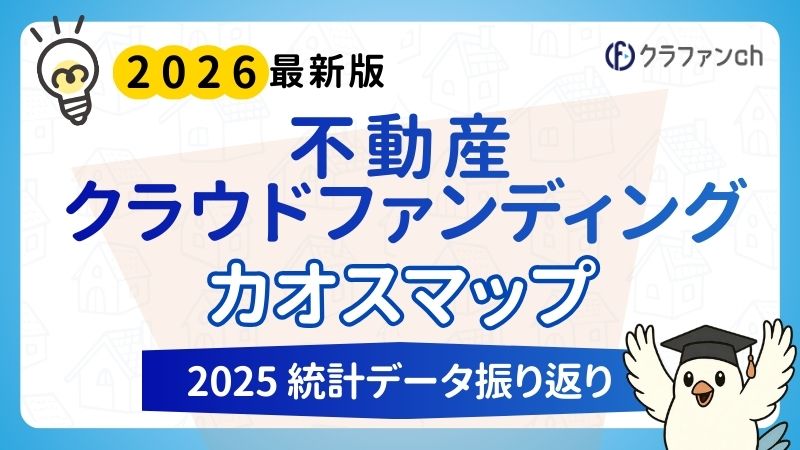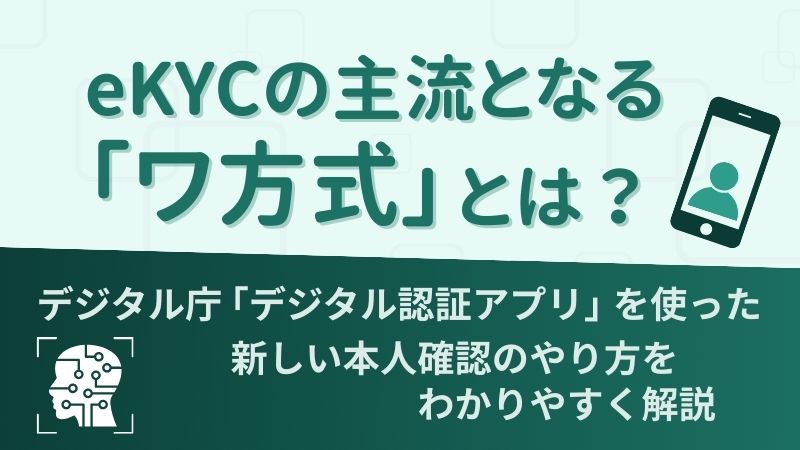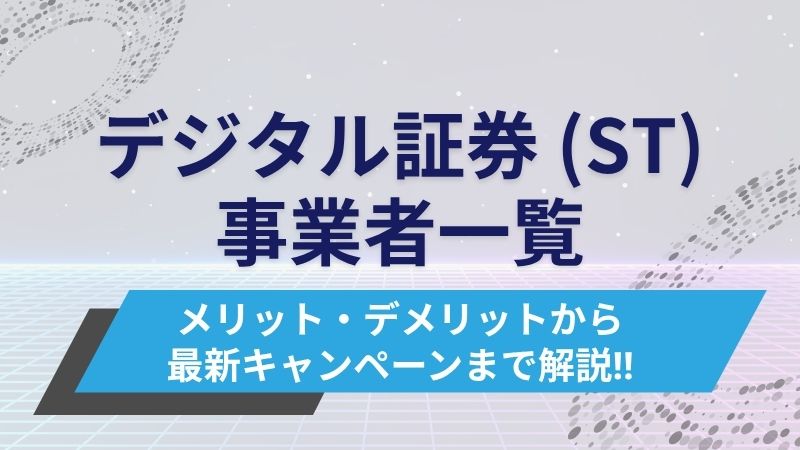不動産クラウドファンディングは、少額から始められる新しい投資手法として注目を集めています。
不動産クラウドファンディングは、少額から始められる新しい投資手法として注目を集めています。
一方で、元本割れや配当遅延といった“失敗”リスクもゼロではありません。
この記事では、実際の事例をもとに、失敗しやすい投資家の特徴と対策を解説します。
安心して投資を始めるために、正しい知識と判断力を身につけましょう。
不動産クラウドファンディングとは?
不動産クラウドファンディングとは、複数の投資家がインターネット上で資金を出し合い、不動産の取得・運用・開発などのプロジェクトに少額から投資できる仕組みです。主に「匿名組合契約」や「任意組合契約」として締結され、不動産特定共同事業法などの規制下にあります。近年では1万円から始められる商品も登場し、初心者でも不動産投資に参加しやすくなっています。
REIT(不動産投資信託)と異なり、クラウドファンディングでは個別の不動産案件に出資できる点が特徴です。物件の立地や運用計画を自ら選べる一方で、元本保証がないなど、リスクを自分で見極める力が求められます。
「失敗」とは何を指すのか?
不動産クラファンにおける「失敗」は、次のような状態を指します。
- 元本割れ(出資金が回収できない)
- 配当の遅延や未配当(想定通りに分配されない)
- ファンドの償還遅延(予定通りに運用が終了しない)
これらは「想定した収益が得られない」「資金が戻ってこない」リスクを意味します。
たとえ物件が運用されていても、工事の遅延や売却活動の難航、融資の遅れなどにより、投資家の期待収益に到達しないケースもあり得ます。
実際に起きた失敗事例
ダイムラー・コーポレーション:破産(2025年7月)
不動産クラファン業界において大きな衝撃となったのが、《ダイムラー・コーポレーション》の破産です。横浜市に本社を置く同社は、主に開発型の不動産クラウドファンディング『DAIMLAR FUND』を展開していました。2025年7月18日、横浜地方裁判所より破産手続開始の決定が下され、ファンドの匿名組合出資者は劣後債権として扱われることが明らかになりました。
2025年7某日、筆者宛に横浜地方裁判所から「破産手続開始決定通知書」が届きました。債務者は「株式会社ダイムラー・コーポレーション」。筆者自身、同社が運営していた不動産クラウドファンディングに出資しており、唐突な破産手続き開始、[…]
投資家との契約は匿名組合であったため、出資金の回収順位は低く、元本割れとなる可能性が極めて高いと見られています。この件は、不動産クラファンで初の「破産による元本毀損リスク顕在化」として、業界全体に警鐘を鳴らしました。
ヤマワケエステート:想定利回りをはるか下回る配当(2025年6月)
2025年6月30日に運用終了した『ヤマワケエステート』の「第100号 京都府八坂・祇園エリア 商業地ファンド」では、実績利回りが想定を大きく下回る結果となり、一部投資家の間で失望の声が広がりました。
当該ファンドは、2024年8月から2025年6月までの約11カ月間運用され、想定利回りは17.8%として出資者を募りました。多くの案件で高利回りが訴求されてきた同社ですが、本案件の実績利回りは約3.69%にとどまりました。
この結果は、当初の「高利回り」を期待して出資した投資家にとっては、想定と現実のギャップが大きい事例といえ、不動産クラウドファンディングにおいて利回りの「目安」と「実績」の違いに対する投資家の理解促進と、透明性ある開示の必要性を再確認させるものとなりました。
みんなで大家さん:行政処分(2024年)
2024年、『みんなで大家さん』シリーズの販売会社である《みんなで大家さん販売株式会社》および、ファンドの組成・運用を担う《都市綜研インベストファンド株式会社》は、計画変更時に出資者への十分な説明を行っていなかったとして、東京都および大阪府より一部事業に対する営業停止命令を含む行政処分を受けました。
この「シリーズ成田ファンド」では、2019年10月に千葉県成田市における開発計画において、成田市からの開発許可および千葉県からの農地転用許可を取得後、造成工事を開始。当初は2021年3月末の完成を予定していました。しかし、その後3度にわたる計画延長が申請され、最終的には当初計画から4年8カ月遅れの進行となっています。こうした状況下でも、同ファンドは「想定利回り7%」を掲げ、これまで2カ月ごとの配当を継続していました。
ところが、2025年1月時点でも土木工事の進捗率は約8割にとどまり、プロジェクト全体としてはわずか2.3%の進捗率にとどまっていることが判明。これを受け、一部出資者の間では「今後も配当が継続されるのか」と不安の声が上がっていました。
そして、2025年7月31日には出資者宛に分配金の支払い遅延を通知する案内が発行され、懸念が現実のものとなっています。
なお、東京都および大阪府が公表した行政処分の主な理由は以下の通りです。
- 重要事項説明書に虚偽の記載があった
- 契約変更時に投資家の事前同意を取っていなかった
- 資金使途の不透明さ
これらの事案は、不動産クラウドファンディングにおける情報開示の透明性や出資者保護の重要性を再認識させるものです。特に、契約内容の変更に関する事前同意の欠如は、投資家の信頼を大きく損なう結果となりました。
失敗しやすい投資家の特徴

利回りの高さだけで選んでしまう
投資初心者にありがちなのが、「年利8%」「配当率10%」といった高利回りに惹かれて投資先を決めてしまうことです。しかし、これらの利回りはあくまで“想定”であり、実現が保証されているわけではありません。利回りだけで判断すると、リスク説明や運用スキームの詳細を見落とし、結果的にトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
運営会社の実績や財務状況を調べない
事業者の信頼性は、不動産クラファンの成否を大きく左右します。過去にどれだけのファンドを運用し、何件が無事償還されたか、配当遅延や元本毀損の事例がないかなど、事前に調べることが重要です。特に財務諸表や親会社の信用格付け、運営メンバーの経歴なども確認しておくと安心です。
スキームの内容を理解していない
「匿名組合契約」「任意組合契約」「優先劣後構造」など、聞きなれない言葉が多いクラウドファンディングの世界。仕組みを理解しないまま投資してしまうと、想定外のリスクを背負うことになります。投資家は元本が最優先で返ってくるわけではないという点は、特に注意が必要です。
一つの案件に多額投資する
「ここなら大丈夫そう」と直感で判断し、複数案件に分散せず一つに大金を投じてしまうのは大きなリスクです。万が一その案件が延期・失敗となった場合、資金拘束や損失がダイレクトに影響します。たとえ信頼できる事業者でも、分散投資は鉄則です。
失敗を防ぐチェックポイント
不動産クラウドファンディングを成功させるには、事前に以下の5つのポイントを丁寧に確認することが欠かせません。投資先の選定でこのチェックを怠ると、元本割れや配当遅延といった“想定外のトラブル”に直面するリスクが高まります。
- 登録・許認可の有無をチェック:不動産特定共同事業登録があるかを確認。
- 優先劣後構造があるか確認:投資家保護の仕組みがきちんと組み込まれているか確認。
- スキームの内容を把握:開発型か運用型か、倒産隔離がされているかなども重要な判断材料です。
- 投資対象の詳細を確認:立地や売却想定価格、利回りの根拠などが明確かどうか。
- 分散投資を意識する:少額から複数のファンドに投資し、リスクヘッジを行いましょう。
登録・許認可の有無をチェック
まず基本中の基本ですが、投資先の運営会社が「不動産特定共同事業」の登録があるのかを確認しましょう。登録がないまま営業している事業者は、法的にグレーまたは違法の可能性があり、行政処分や突然の運営停止のリスクが高くなります。公式サイトや国交省・各都道府県の公表情報から確認可能です。
優先劣後構造があるか確認
不動産クラファンには、出資金の一部を運営会社自身が劣後出資として負担する「優先劣後構造」があります。この構造があると、万が一物件の売却価格が想定より下回った場合でも、まずは運営側の出資分から損失を吸収し、投資家の元本保全を優先してくれます。劣後出資比率が20〜30%程度あると、一定の安心感があります。
スキームの内容を把握
案件には大きく分けて「開発型」と「運用型」があります。開発型は利回りが高い分、建築中止や許認可遅延といったリスクがあります。一方で、運用型は既存の賃貸物件が多く、収益が比較的安定しているとされます。また、資金が運営会社の倒産に巻き込まれないよう、信託口座や分別管理がなされているか(=倒産隔離スキーム)も確認すべき重要ポイントです。
投資対象の詳細を確認
投資する物件について、「どこにあるのか(立地)」「どのくらいの期間で運用するのか」「利回りは何を根拠にしているのか」などが明確に説明されているかをチェックしましょう。情報の開示レベルが低い案件や、利回りだけが強調されているファンドは、リスクの把握が難しくなりがちです。運営会社の説明責任の姿勢も見抜く材料になります。
分散投資を意識する
「どれだけ調べても100%はわからない」という前提で、1つの案件に資金を集中させないことが鉄則です。1万円〜5万円の少額からでも始められるクラファンの特性を活かして、複数の案件・事業者に分けて投資することで、万が一の遅延や損失を他でカバーできる体制を整えることができます。分散こそ最大のリスク管理です。
信頼できる業者選びのポイント
 不動産クラウドファンディングの成功には、「どの事業者を選ぶか」が大きく影響します。高利回りや話題性に目を奪われがちですが、投資先の信頼性をしっかり見極めることが最優先です。以下に、信頼できる業者を見抜くための判断基準を詳しく解説します。
不動産クラウドファンディングの成功には、「どの事業者を選ぶか」が大きく影響します。高利回りや話題性に目を奪われがちですが、投資先の信頼性をしっかり見極めることが最優先です。以下に、信頼できる業者を見抜くための判断基準を詳しく解説します。
- 不動産特定共同事業の登録有無
- 償還・配当実績の開示(過去の配当率、償還完了率など)
- 劣後出資比率の高さ(投資家保護の指標)
- 親会社やグループ会社の信用力
- ファンド情報やリスク開示の透明性
クラファン市場は新興分野であるため、誰もが知る大手企業が参入しているケースはまだ限られています。だからこそ、透明性や誠実な対応を積み重ねている事業者を選ぶことが成功のカギになります。
クラファンは「人」ではなく「仕組み」で選ぶ
SNSなどで「この会社の担当者が丁寧だった」「◯◯さんに勧められて投資した」などという投稿を目にすることがありますが、クラウドファンディングはあくまで契約とスキームに基づく投資。個人の印象や対応よりも、制度設計や企業の実力、透明性が最も重要です。
誠実な運営体制と、明確な情報開示。これらを兼ね備えた業者を選ぶことで、不動産クラファンのリスクを大きく抑えることができます。
他の投資とのリスク比較
| 投資種別 | リスク | リターン | 流動性 | 主な懸念 |
|---|---|---|---|---|
| 株式 | 高 | 高 | 高 | 価格変動リスク、高頻度取引のストレス |
| REIT | 中 | 中 | 中 | 市場連動リスク、金利上昇による価格下落 |
| 不動産クラファン | 中 | 中 | 低 | 運営会社・物件リスク |
クラファンは、株式のようにリアルタイムで取引することはできず、運用期間中は基本的に資金拘束される点が特徴です。ただし、値動きがないため心理的ストレスは少ないというメリットもあります。
よくある質問(Q&A)
Q:元本割れはどれくらいあり得る?
A:2025年7月のダイムラー・コーポレーションの破産が象徴するように、発生確率は低いもののゼロではありません。特に開発型案件や、優先劣後構造が設定されていない案件は注意が必要です。
不動産クラウドファンディングに取り組むうえで考慮すべきリスクの1つが元本割れです。2025年6月現在不動産クラウドファンディングにおいて元本割れが発生した事例はありませんが、一定のリスクがあることは理解しておくべきでしょう。[…]
Q:配当遅延や償還遅延の理由は?
A:建設遅延や天候不順、販売先不在、融資未実行などが代表的な要因です。過去にそうしたトラブルを抱えた事業者が、事前に説明しているかも要確認ポイントです。
不動産クラウドファンディングは手軽に始められる一方で、「償還遅延」という見落としがちなリスクも存在します。本記事では、2025年7月現在で確認された償還遅延が発生してしまった案件を一覧にし、運営会社ごとの対応姿勢や傾向を投資家目線で分析しま[…]
Q:税制面の注意点は?
A:クラファンの配当金は原則「雑所得」に分類されます。会社員の副収入が20万円を超えると確定申告の義務が生じるため、税理士や確定申告アプリなどで対応しましょう。
→合わせて読みたい
〜投資型クラウドファンディングの税務対応を正しく理解しよう〜不動産クラウドファンディングを含む「投資型クラウドファンディング」で得た収益には、確定申告が必要となるケースがあります。特に、「雑所得としての課税」「源泉徴収」「20万円ルール[…]
まとめ
不動産クラウドファンディングは、少額から不動産投資に参加できる画期的な手段として、多くの個人投資家に注目されています。REITや株式とは異なり、自分で物件や運用方針を選べる自由度の高さが魅力ですが、その分、元本保証がない・流動性が低いといった特有のリスクを伴うことも忘れてはなりません。
実際に、ダイムラー・コーポレーションのような運営会社の破綻や、行政処分を受けた事業者も存在しており、「クラファン=安心」とは言い切れないのが現実です。利回りの高さだけで選ぶのではなく、契約内容・事業者の実績・スキームの構造まで丁寧に確認し、自分の投資判断で納得したうえで出資することが重要です。
本記事で紹介した「失敗しやすい投資家の特徴」や「チェックポイント」を活用すれば、リスクをコントロールしながら不動産クラファンをうまく活用することが可能です。また、信頼できる運営会社を見極め、複数ファンドに分散投資することで、安定的な資産形成の一手として活かせるポテンシャルもあります。
不安な点があれば、事前に問い合わせをしたり、複数の事業者を比較したりする慎重さも大切です。リスクと向き合いながら、正しい知識と判断力を身につけて、あなたに合った不動産クラファン投資をスタートしてみてください。