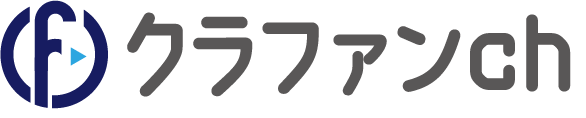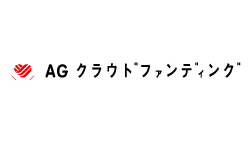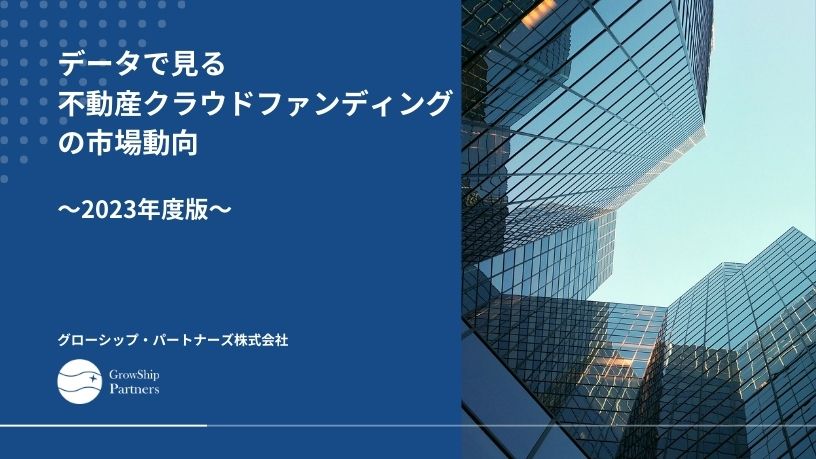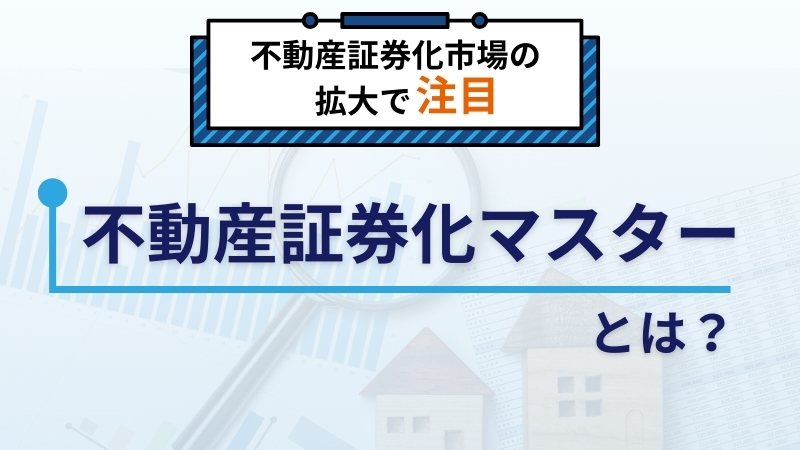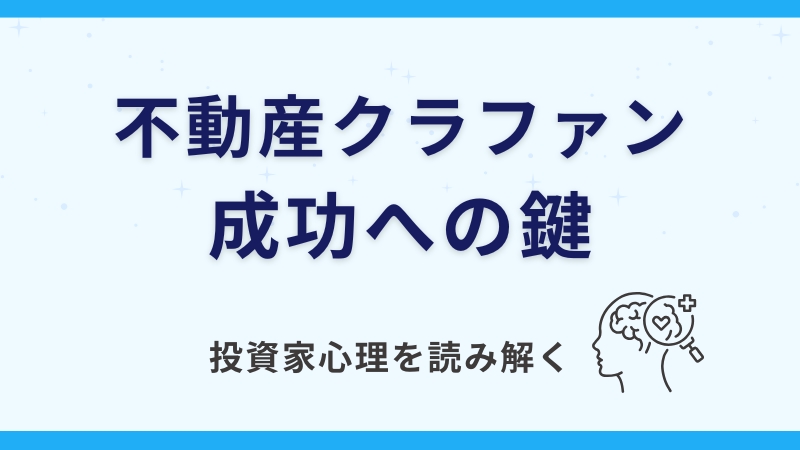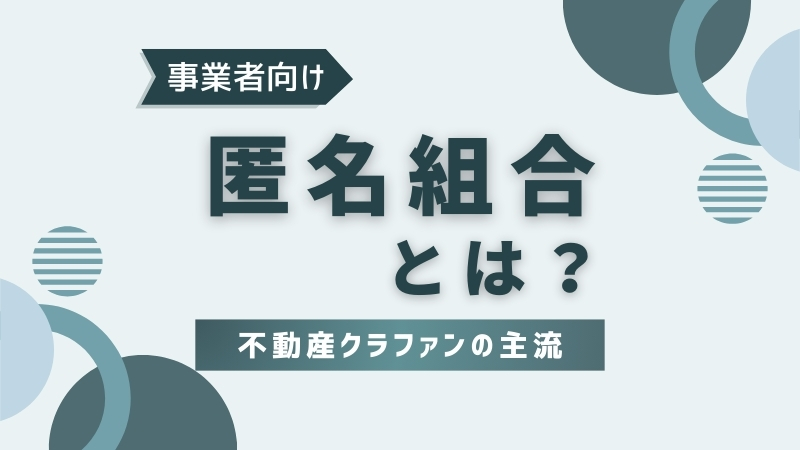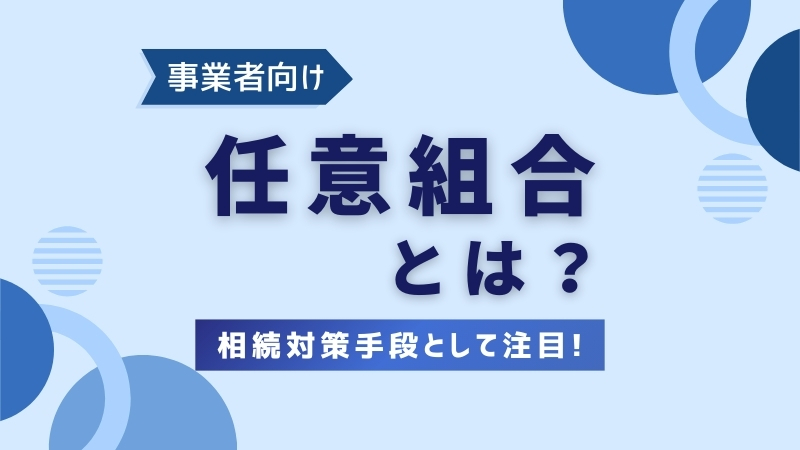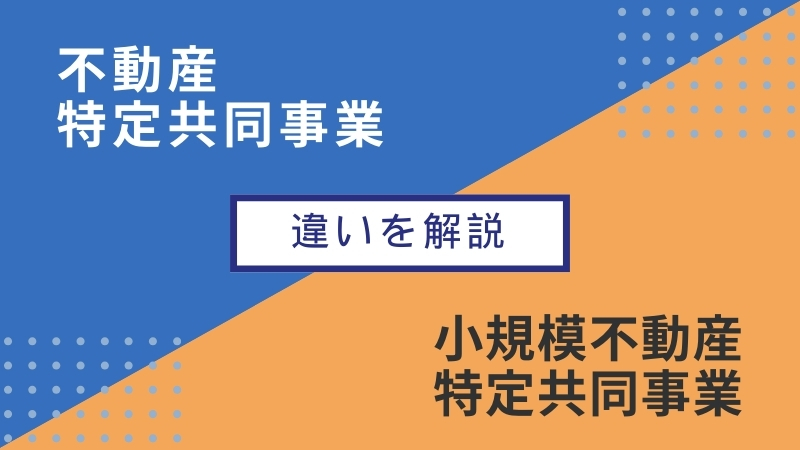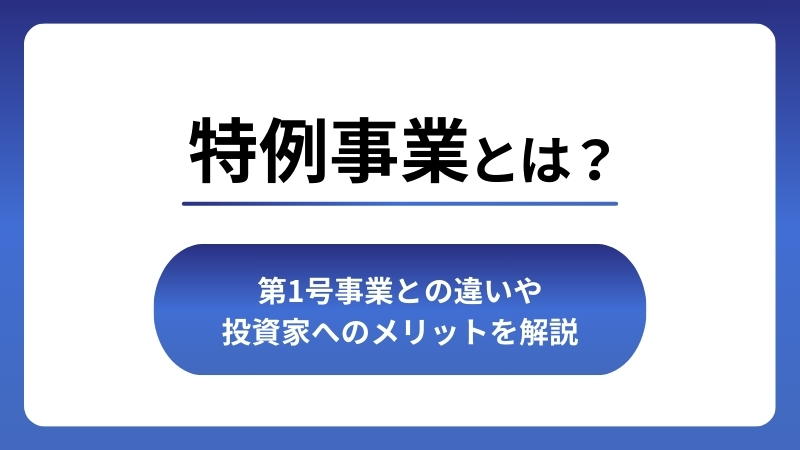融資型クラウドファンディングで資金調達すると、借り手にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
また、銀行からの借り入れなどの従来の資金調達の手段とは何が異なるのでしょうか。
この記事では、融資型クラウドファンディング事業への参入を考えている金融事業者の方や、クラウドファンディングでの資金調達を検討している事業者の方へ、クラウドファンディングで資金調達することのメリットや特徴、注意点を解説していきます。
資金調達の手段としてクラウドファンディングが選ばれる理由
資金調達手段として、融資よりも適切と判断されるケースがあるため
事業のための資金調達手段として融資よりも適切と判断され、融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)が選ばれるケースがあります。
資金調達手段として、融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)が適切と判断される代表的な理由としては、以下のものがあります。
・銀行との取引実績が短い
・直近決算が赤字
・ビジネスモデルが新しすぎる
・借入金額が少額
・借入期間が短い
・融資額に一定の上限が付けられている
・すぐに返済したい
このように銀行からの融資で生じる課題を、クラウドファンディングでは解決できる可能性があり、状況によっては適切と判断される場合があります。
迅速な資金調達を実現可能
融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)で資金調達をする大きなメリットの1つは、すぐに資金を借り入れられる点です。
金融機関を介した資金の借り入れは低金利故に審査に時間がかかり、審査に通ったとしても資金調達できるまでにさらに時間がかかる場合があります。
金融機関よりも高い金利となってしまう反面、クラウドファンディングは、インターネット経由で不特定多数の投資家から資金を集められる仕組みであるため、スピーディーな資金調達が可能です。
個人投資家へのアピール
融資型クラウドファンディングでは、個人投資家から自分達の事業を説明して資金を募るため、銀行借入にはない「個人投資家へのアピール」が可能であるため、資金調達と同時に、投資家へのPRも目的とするケースがあります。
クラウドファンディングでは、プラットフォーマーのサイト上にプロジェクトを掲載するため、自社や事業について知ってもらい、納得した上で資金を提供してもらうことができます。
クラウドファンディングで資金調達をする代表的な事業者
融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)で資金調達をする事業者の代表的な例は、以下の通りです。
不動産事業者:不動産を仕入れて、開発し、販売するまでのつなぎ資金として利用
再生エネルギー事業者:太陽光発電の施設などを開発し、販売するまでのつなぎ資金として利用
ファクタリング事業者:売掛債権の仕入れ資金として利用
ノンバンク:融資事業で貸し出すための資金として利用
リース会社:リース事業の運転資金やリース資産の流動化として利用
一般事業会社:新規事業やプロジェクトのために、銀行借入や自己資金などとの組み合わせで利用
上場会社:自社のPRや自社商品の宣伝のために利用
海外事業者:上記の事業を海外で展開するために利用
このように、幅広い業種やプロジェクトで、クラウドファンディングでの資金調達が利用されています。
クラウドファンディング事業者の審査も甘くはない
銀行もクラウドファンディングも、審査は厳正に行われています。
融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)各社の審査担当者は銀行や商社などで審査経験がある人が多いので、返済能力についてはシビアにジャッジされます。
クラウドファンディングを金融機関に融資を断られた場合の最終手段として捉える、安直な考えは捨て、万全の事業計画を練りましょう。
まとめ
この記事では、資金調達の方法としてのクラウドファンディングのメリットや特徴、注意点を解説してきました。
クラウドファンディングは多くの事業者が参入している分野で、資金調達をスピーディーに完了できる画期的な手段です。
使い方次第では事業のさらなる成長を見込めるので、資金調達の一手段として検討してみてはいかがでしょうか。